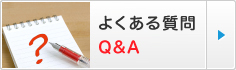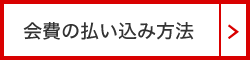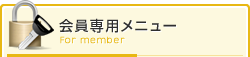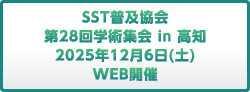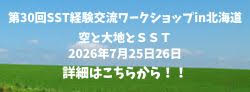各委員会紹介
当協会では、理事会の下に、現在11の委員会が組織され活動しています。各委員会の活動を紹介します。
なお、各委員会の委員長と本部事務局とで理事会執行委員会が組織され、社員総会ならびに理事会で出された方針にしたがって会務を執行するため、おおむね2か月に1回委員会を開催し活動しています。
<将来計画委員会>
将来計画委員会の役割・業務は、SST普及協会の発展のために必要な事業の改善・改革案を提案し、問題提起をすること、協会組織の在り方についての改革案を提起することです。
この役割に沿い本委員会はSST普及協会の事業と組織の問題点を考察し、問題解決の方向を考え、理事会執行委員会に改革の提言を提案してきております。
会議はオンライン会議システムを利用して一年度内に4~6回、2~3か月に1回程度開催しており、時間と経費を節約するようにしております。現在の委員(敬称略、北から)は北海道支部 大川浩子、南東北支部 丹羽真一、北関東支部 飯島久香、南関東支部 天笠 崇、 安西信雄、高橋 恵、東海支部 高木友徳、近畿支部 足立一、九州沖縄支部 高森祐樹の9人です。
2020年度以降に理事会執行委員会へ提案した提言は次の8つです。それらは、
- 2020年 4月 第三の夢「若い人がSSTを知り、入会してくれる事業」をすすめるための提言1
- 2020年 7月 第四の夢「会員のメリットを増やし、会員の満足度を高める事業」提言2
- 2020年 9月 第一の夢「協会の学術レベルを向上させる事業」提言3
- 2021年 2月 2025年の記念行事の一つとして、世界のSSTの発展を知り、良いことを取り入れ、また日本のSSTの発展を伝えるシンポジウム(のようなもの)を企画実行する提言4
- 2021年 5月 5つの夢の実現にむけての行動計画(案)の提言5
- 2022年 8月 様々な領域の若い専門職の中でSSTを普及し会員増強を図るための提言
- 2023年 4月 ワークショップと学術集会のSST普及協会2大行事の今後のあり方についての提言
- 2024年 1月 SST普及協会の財政健全化ヘ向けての提言
今後もSST普及協会の発展のために必要な事業の改善・改革案の提案、問題提起、協会組織の在り方についての改革案を提起してまいります。
(委員長 丹羽真一)
<財務委員会>
財務委員会は池淵恵美委員(南関東支部)、後藤雅博委員(北関東支部)、加瀬(南関東支部)の3名で構成されています。
財務委員会の主な業務として
- 協会予算案の策定
- 予算執行管理
- 募金活動
があり、必要に応じて会費改訂等を理事会・社員総会に提案する作業があります。
前年度の決算を参考に、毎年1月ごろに募金趣意書を作成し、例年7月に開催される予算理事会に予算案を提案していくというのがスケジュールです。
寄附は概ね各製薬会社にお願いしているのですが、年々厳しくなってきています。
各委員会等の業務計画をヒアリングしたうえでの、積み上げ方式の予算立案が本来なのでしょうが、なかなか難しいというのが現状です。また、記念事業や代議員選挙のための積立金もあり、赤字予算の計上が続いておりますので、財政健全化のための抜本的な対策が求められています。これも早急に解決してまいりたいと思います。
会計業務は素人ですので、協会と委託契約を結んでいる非営利法人総合研究所公益総研の税理士の方に適宜ご相談しながら業務を進めています。
(委員長 加瀬昭彦)
<ニューズレター編集委員会>
SSTニューズレターはSST普及協会の理事会のもとで活動している「SSTニューズレター編集委員会」の編集により、年2回発行されています。
編集委員長は溝渕博美、副編集委員長は林史学、編集委員として上村嵯知、磯上あづさ、河岸光子、清水有香の構成で編集委員会を開き、企画・編集をしています。SSTの広がりに応じた特集や実践報告、支部の活動紹介、協会の二大行事の紹介、会員からのQ&Aに答えるコーナーなど、役に立つ情報誌を目指しています。会員の意見を反映させた紙面作りのために、アンケートも実施しています。
125号からはWEB発行をしていますので、創刊号から最新号まで「ニューズレターアーカイブ内容公開中」から会員専用ページへログインして閲覧ができます。WEB発行と同時に紙面でのダイジェスト版の発行も始めました。ダイジェスト版で興味のある記事はぜひWEB版でお読みください。
(委員長 溝渕博美)
<研修委員会>
研修委員会は、SST普及やそれに関連する研修等の運営、そして更なる発展を目指した検討や議論を行っている委員会です。
また、SST普及協会には、研修会講師や地域等でのスーパービジョンを行う「認定講師(
http://www.jasst.net/top/lecturer
を参照)」という資格がありますが、その資格審査の実施も当委員会が担当しております。
所属委員はベテランから若手まで、そして北から南の支部までの20名弱で構成され、研修の内容や在り方、実際的な開催方法に至るまで、様々なテーマについて活発に議論が交わされています。
研修事業の他に行っていることとしては、「テキスト・マニュアル等の研修資料のデータ管理/改訂/開発」、「認定講師メールマガジンの発行」等があります。
認定講師の皆様をサポートするとともに、新しくSSTの扉を開こうとしている皆様に、より効果的でより適切な内容の研修をお届けできるよう、今後も工夫を重ね取り組んでまいります。
(委員長 小山徹平)
<広報委員会>
広報委員会は「日本中、どこに住んでいてもSSTの情報が届くように」と活動しています。委員は各支部から選出された11名で構成されています。
主な活動として、FacebookやX(旧Twitter)、そして会員向けのメールマガジン等を活用した各支部の研修情報等の発信や、全国経験交流ワークショップや学術集会等の情報のお届けとなります。他にも大会の会場からその様子を動画も含めて配信する等、時世に合わせた取り組みをして参りました。
現在、Facebookのフォロワーは1,359人、Xのフォロワーは275人(2024.2.22)となります。FacebookやXを委員会からの一方向の情報発信に留めず、それを読んでいただいた人、目にしていただいた人との双方向ツールにしたいと思っています。一度「一般社団法人SST普及協会」のページをご覧ください。各支部のお知らせは、支部ホームページも活用していますので、ご覧ください。
Facebook(https://www.facebook.com/jasst.pr.tf/)、X(https://twitter.com/JAPANSST/)
またYouTubeには「SSTチャンネル」があり、e-ラーニング委員会と協力しながら多くの方にチャンネル登録していただけるよう、そして動画を活用していただけるよう広報していきたいと考えています。是非!チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。
広報委員会はSSTに関心のある方との情報のパイプ役となり必要としている、あるいは欲しい情報は何かということにアンテナを張っています。
何かご要望があれば、FacebookやX、支部ホームページ(事務局のメールアドレスがあります)からどんどんご連絡ください。
(広報委員会一同)
<学術委員会>
みなさまこんにちは。学術委員会の福永です。
学術委員会の役割は、1.普及協会が実施する全国大会の運営をサポートすること、2.全国大会等において大会シンポジウムを企画実施すること、3.研究発表等における研究倫理規定を整備するなど実践や研究の質を維持し高めること、です。現在は、各支部から様々な実践や研究経験をもった委員が私を含めて8名おり、委員間で協力しながら各活動を担っています。
1については、開催される支部や現地実行委員の方々と共に、全国大会の運営を担っています。コロナ渦で対面での大会実施ができなかった時期もありますが、オンラインの活用や対面とのハイブリット開催等により、開催運営のノウハウを蓄積してきました。今後も全国各地でSSTに関わっているみなさんと共に、大会の成功に寄与できればと考えています。2について、大会シンポジウムは大会テーマや実行委員会等で寄せられた想いを形にする機会だと思っています。世の中の状況も刻一刻と移ろうなかで、参加された方々の心に残る内容をお届けしたいと考えています。3については、抄録の査読を担うなど、もっとも学術という言葉が持つアカデミックな面になろうかと思います。今後は研究倫理規定の見直し等により、SSTに関する実践や研究が正しいプロセスを経て、広がっていけるようお手伝いしていきます。オンラインジャーナル委員会等を含め、他の委員会活動とも連携しながら、学術委員会のお役目を果たしていきたいと考えています。
今後も、みなさんにとって身近なSSTがより多くの方々にわかりやすく伝わり、広がっていけるよう願っています。全国大会でぜひお会いしましょう。
(委員長 福永佳也)
<e-ラーニング委員会>
e-ラーニング委員会は、2022年に発足した新しい委員会です。インターネットでの配信を活用した取り組みが日常のものとなった現在、SST普及協会でも会員の方々への情報発信を強化していきたいと考えています。
活動としては、SSTチャンネルをはじめとする、インターネットを活用したコンテンツの充実を図っていくこと。学術集会や経験交流ワークショップなどの配信。教育的な研修動画のコンテンツ作成。などなど…色々なことにチャレンジしていきたいと考えていますので、会員の皆様からも是非とも、色々な意見をお聞かせください。
(委員長 村本好孝)
<出前講座委員会>
当協会では、心理教育・家族教室ネットワークと協力して、各病院や施設に出向いて研修を行う出前講座(精神障害者の地域生活支援技術者養成講座)を実施しています。多くの病院や施設では、患者さんたちの自立や地域生活の向上に向けて職員研修に力を入れていますが、職員を院外研修に出しても、学んだ理念や方法を職場に定着させることは稀と言われています。そこで、経験のある講師陣が病院や施設に出向いて多数の職員を対象として研修を実施することが効果的と考え、ご依頼があれば次の講座を実施出来る準備をしています。
出前講座の委員は、下記の6人の担当と、増田直子委員の計7人です。出前講座の実施にあたっては、出前講座マネジメント委員会にご協力いただいています。
次の6講座あり、1講座3時間が1単位です(家族支援は2単位)。
- 急性期入院治療を活性化し再発防止力を高めるための講座(担当:加瀬昭彦委員)
- 長期在院患者の退院支援を活性化するための講座(担当:安西信雄委員)
- 参加者が魅力を感じるデイケアにステップアップするための講座(担当:池淵恵美委員)
- 個別支援SSTにより、回復を一段と促進するための講座(担当:浅見隆康委員)
- 家族支援と家族への心理教育を学び実践するための講座(担当:後藤雅博委員)
- スタッフの質の向上のための講座(担当:河岸光子委員)
(講座の説明や申込み方法はhttp://www.jasst.net/top/delivery_lectureをご参照ください)
この出前講座については、2014年10月に公益社団法人 日本精神科病院協会に協力を申入れ、同協会の常務理事会で承認されています。医療機関からのご依頼を歓迎しますが、就労支援や地域生活支援、教育分野の学校教員・支援者向け講座、発達障害など、病院(医療)以外の教育や地域支援領域のニーズへの対応も検討しているところです。
なお、新型コロナやインフルエンザなどへの対応につきましては、お申し込みいただいた施設の連絡担当者の方とご相談の上、安全が確保された状況で講座を実施しています。関心をお持ちの方は上記のURLのお申込先にご連絡ください。
(委員長 安西信雄)
<オンラインジャーナル委員会>
SST普及協会は2021年7月9日の理事会で「SSTニューズレターは今後印刷・郵送ではなくオンラインで発行すること、協会としてオンラインジャーナルの発行を目指すこと」という方針を決めました。新しい時代に対応してオンラインを活用していこうということですが、SSTや関連領域の学問的発展・情報交流を図るため、自由度の高い学術誌の発行をオンラインジャーナル委員会で検討しています。
この委員会は、ニューズレター編集委員会をはじめとする各委員会代表から構成され、委員長は副会長である安西がつとめています。オンラインジャーナル委員会では、オンラインジャーナルを次のようにイメージしています。
- 原著や総説などの投稿論文を受けて査読を行って掲載する。
- 協会イベントにおける学術的講演、基礎的・教育的な講座を掲載する。
- 気軽に読める経験談や実践報告、エッセイなども掲載する。
- オンラインのメリットを生かして、記事に関連した画像や動画も提供する。
オンラインジャーナル委員会のもう一つの重要な役割は実現可能性の検討です。関連領域だけでも多数の雑誌があり、投稿論文が減って苦労している雑誌が多い中で、新たに立ち上げて投稿があるのかが心配ですし、現場の方々のニーズがどこにあるのかを解明することも課題です。さらに、投稿・査読、編集作業や、雑誌のオンライン掲載などの仕組みをどうするか、効率的な運営の仕方と赤字を出さない財政面の検討が必要です。委員会ではこれらの課題を引き続き検討するとともに、心理教育・家族教室ネットワークをはじめとする、関連する学会や団体へのアンケートを実施してご意見をうかがっているところです。
以上のように、オンラインジャーナルはまだ企画の段階ですが、協会設立30周年(2025年)に向けての「夢のある協会事業」では、「第一の夢 協会の学術レベルを向上させる事業」の一つとして「協会学術誌発行(オンラインジャーナル)」を掲げています。オンラインジャーナル委員会では、関連学会や団体のご意見をいただきながら、企画の具体化を進めていきたいと考えていますので、協会会員のみなさまのご理解とご協力をお願いする次第です。
(委員長 安西信雄)
<医師層対策委員会>
SSTは患者のリカバリーに重要なツールであるが、残念ながら精神科医のなかでは知名度が低い技法になっています。医師層対策委員会は、医師にSSTを正しく理解してもらい、広く実践につなげる目的のために作られた委員会です。精神科医療のなかでは、医師が治療のイニシアチブをとることも多いので、全国どこでもSSTにアクセスできる環境の実現のためには医師の協力は不可欠と考えています。委員は土田正一郎会員(北海道支部)、浅見隆康会員(北関東支部)、天笠崇会員(南関東支部)、和田明会員(南関東支部)、植田俊幸会員(中国支部)、渡邊朋之会員(四国支部)、高橋の7名からなっています。
喫緊の課題は、新規医師会員の開拓です。そして地域における、あるいは支部におけるSST普及活動に率先して取り組んでいただく人材を育成していくことです。
これまでの委員会活動は、主に精神神経学会でシンポジウムやワークショップを行い、宣伝に努めることに重きが置かれていました。さらに医師会員向けアンケート調査を行い、その結果から、“SSTは診療に役立つ”と多数寄せられ、役立った事例を公募し、昨年のSST普及協会の学術集会で、会員の皆様に広く紹介をさせていただきました。大会長や事務局のご尽力のおかげで多くの若手医師に参加いただきました。引き続き、精神療法の中でSSTを紹介したり、産業医関連でSSTの話を入れたりすることで、医師に対しての魅力的な企画を立てたいと考えています。協会では丹羽会長を中心に、「新しいSSTの教科書」の企画が進んでいます。この中で、普段の診療の中で個々の患者の面接治療場面に用いることができるSSTを紹介する、といった部分があります。ここには医師会員の日頃の経験が役立つと思います。また地域や支部における活動に医師層の積極的な協力も重要と思っています。
現在協会では5つの事業を計画しています。これらの計画が円滑に進んでいくためには医師会員の一層の協力と、並びに新規に入会した医師会員の人材育成が必要です。このようなことを念頭に、当委員会もしっかりと活動していきます。
(委員長 高橋恵)
<パブリックリレーションズ(PR)委員会>
PR委員会は、名称が「広報」と紛らわしいのですが、もともとパブリック・リレーションズとはいわゆる広告の意味だけではなく、一般の人や様々な組織に対して理解や信頼を獲得しようとする目的で行われる活動全般を指します。令和元年度まであった、政策委員会と渉外委員会を改組して新しいひとつの委員会としたものです。
委員会の性質上、各職能団体とのつながりが重要なので委員は各職種から構成されており、現在の委員は看護職(村本好孝、渉里さやか)、精神保健福祉士(白戸里見、瀧本優子)、作業療法士(坂本浩)、矯正保護領域(品田秀樹)、心理領域(佐藤幸江)、教育(品田卓磨)、医師(安西信雄、後藤雅博)の10名で、委員長は後藤が務めていますが、それぞれの職種の村本、瀧本、坂本、品田(秀)、佐藤、品田(卓)、安西の各委員に副委員長をお願いしています。
現在委員会体制の構築と事業内容の検討中ですが、基本的には政策委員会と渉外委員会の事業を発展的に継続していくことが目標です。政策委員会はもともと国レベルの政策提言も視野に入れた活動と全国レベルの団体との連携を目的としており、渉外委員会はそれに重なる部分もあるのですが、関連する学会、団体との情報共有や共同作業の推進などを主たる業務にしていました。
それに沿って、これまで各委員が独自にそれぞれの領域で行っていた研修会やセミナー開催への協力などをPR委員会の活動として位置づけ、それへの支援、協力を行う予定にしています。ただ2020年度、2021年度は新型コロナ感染対策のため、多くの機関では研修やセミナーが中止になっており、今後の実施体制を検討しているところです。
今後も各現場や研究分野の意見を集約しつつ、各種団体との協働、連携を図り、政策提言にまでつながるような活動を目指したいと思っていますので、ご協力をよろしくお願いします。
(委員長 後藤雅博)